【ワークショップの進め方完全版】失敗しないための3つのポイントとは?
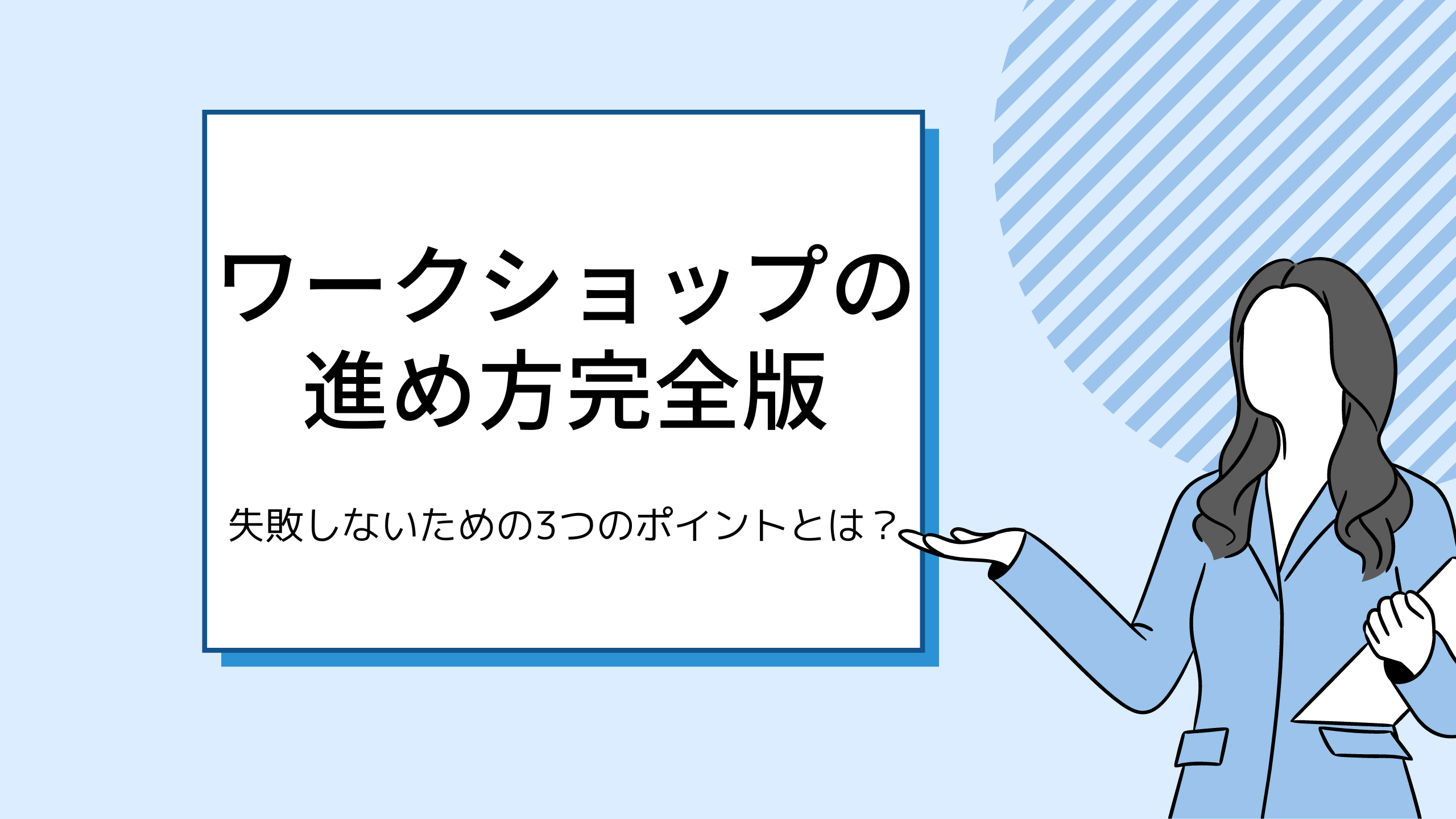 ワークショップは、グループで問題解決やアイデア出しをするための場であり、企業や学校などでよく用いられます。しかし、ワークショップを行う際には、進め方に注意が必要です。本記事では、ワークショップを成功させるための3つのポイントについて解説します。
ワークショップは、グループで問題解決やアイデア出しをするための場であり、企業や学校などでよく用いられます。しかし、ワークショップを行う際には、進め方に注意が必要です。本記事では、ワークショップを成功させるための3つのポイントについて解説します。
参考記事▶︎▶︎▶︎ワークショップとは?目的から具体例、注意点まで完全解説!
目次
- 失敗するワークショップとは?
- 成功するワークショップの進め方
- まとめ
法人向けの様々なプログラム
「研修を実施しただけ」で終わらせません。
行動変容にコミットし、実際の成果が出るまで伴走します。
個人で実用的な知恵を得る
自身のタイミングで必要な知識やスキルを学びたい
失敗するワークショップとは?

近年、全国各地でさまざまな分野のワークショップが開催され、多様化してきています。参加者が主体的に考え、新しい学習を体験するイベントですが、開催する立場となった時、成功するワークショップと失敗するワークショップにはどんな違いがあるのでしょうか。まずは失敗するワークショップになってしまう要因を以下3点紹介します。
- 目的やゴール設定が明確でない
- プログラムの準備が不十分
- 参加者のモチベーションを高める工夫がない
ゴール設定が明確でない
1点目はワークショップの目的やゴールが明確ではないことです。正確には、ワークショップ自体の目的やゴールが不明確な場合と、参加者にワークショップに共有されていない、あるいは共感を得られていない場合があります。
開催前の企画段階で、ワークショップの目的やゴールおよび、参加者のニーズを明確化しましょう。特に企業や組織で行う場合は、参加者の条件やバックグラウンドも考慮し、情報を事前に収集した上でゴールを設定することが重要です。そのうえで目的・ゴールをどのように伝えるのかを具体化していくことが必要です。
プログラムの準備が不十分
企画段階が順調でも肝心のプログラムの準備が不十分であると、ワークショップの価値を充分に参加者に体感できずに終わってしまいます。
ワークショップは主に体感型のイベントですので、参加者が主体的に参加できるプログラムの準備や、全ての参加者が発言できるようなルール、雰囲気作りなど、細部まで想像してプログラムを設計していきましょう。
参加者のモチベーションを高める工夫がない
ワークショップ参加者のモチベーションは十人十色で、中には受け身的な参加になっている人もいることでしょう。開催側は参加者の意欲が高まるよう工夫を凝らす必要があります。
ユニークな体験、参加者同士の交流、ゴールへの共感など工夫すべき場面はたくさんあります。デザイン思考を取り入れたワークショップや、アート、音楽などを活用した創造的なものづくりの場を提供することで、参加者の関心を引き出すことができます。
成功するワークショップの進め方

ワークショップの失敗する要因をふまえ、どうすればワークショップを成功に導けるのか、事前準備の段階から実施の際におさえておくべきポイントを解説していきます。
- ワークショップ実施時の一般的な進め方
- ここが重要!抑えるべき事前準備のポイント
- ワークショップを効率的に進めるための工夫3つ
ワークショップ実施時の一般的な進め方
ワークショップには、内容によりますが、一般的な進め方の型がありますので、参考にしてみてください。それぞれのフェーズで留意すべきことも併せて紹介していきます。
1-1. ワークショップの目的・ゴールとグラウンドルールの共有
ワークショップ冒頭では、目的・ゴールを共有する時間を設けます。この時間は単に進行役が説明するだけでなく、参加者からも期待や目標を引き出し、共通理解を築く大切な機会です。参加者全員がワークショップを通じてどのような状態を目指すのかをイメージできるよう、具体的な事例や成功体験を共有することが効果的です。
また、この段階でグラウンドルール(場の約束事)を共有することも非常に重要です。以下のようなグラウンドルールを参加者全員で確認することで、安心して意見が出せる環境を共に創ることができます:
• 「他者の意見を否定しない」
• 「一人ひとりの発言を尊重する」
• 「守秘義務を守る(ここで話されたことはここだけの話)」
• 「途中退席OK、質問OK」
• 「失敗を恐れず、ためらわず発言する」
• 「他者の時間を尊重する(独占しない)」
これらのルールは、見える場所に掲示しておくと良いでしょう。また、参加者自身にルールを追加してもらうことで、より主体的な場づくりが可能になります。共有したグラウンドルールは、ワークショップ全体を通じて参照できるようにしておくことで、安全で創造的な対話の場を維持することができます。
1-2. アイスブレイク
次に、参加者同士の心理的安全性を高める雰囲気作りとして、アイスブレイクを実施することをおすすめします。ワークショップの内容に関連するオリジナルなアイスブレイクを企画したり、「他己紹介」「Good and New」など気軽に実施できるものでも構いませんので、ワークショップの内容に移る前に取り入れてみましょう。また、全員が一言ずつ発言する、「チェックイン」という方法もあります。
大規模なワークショップでは、より工夫を凝らしたアイスブレイクが求められることもあります。参加者の年齢層や職種に合わせて、互いに打ち解けやすい活動を選択することが重要です。
1-3. 個人ワーク
ここからはワークショップの内容に移っていきます。一般的にはまず個人ワークを実施します。この時間は、各参加者が自分自身の考えや感覚に向き合う貴重な機会です。インプットおよびアウトプットの時間を余裕を持って設定し、参加者が自分のペースで取り組めるよう配慮しましょう。
また、質問のある参加者や作業の進んでいない参加者を自然にサポートできる環境づくりも大切です。特に初めてワークショップに参加する人向けには、丁寧な説明と例示を行うとよいでしょう。
1-4. アイディア出し(発散)
個人ワークの後、グループでのアイディア出しの時間を設けます。この段階では、参加者全員で自由に発想を広げ、共に可能性を探索することが目的です。質より量を重視し、評価や批判は一切行わない環境を皆で作りましょう。アイディア出しのための主要な手法としては以下のようなものがあります:
• ブレインストーミング: 自由に思いついたアイディアを出し合う手法で、「批判禁止」「質より量」「自由奔放」「便乗OK」の4つのルールが特徴です
• ABC法: 発想の起点となるキーワードをA、それに関連する概念をB、さらにそこから派生するアイディアをCとして、連想を広げていく方法
• KJ法: 川喜田二郎氏が考案した手法で、個々のアイディアをカードに書き出し、グループ化・構造化していく方法
• マインドマップ: 中心テーマから放射状にアイディアを広げていく視覚的思考ツール
• 強制連想法: 無関係な言葉や画像を組み合わせて、新しい発想を生み出す手法
• オズボーンのチェックリスト: 他の用途は?適応できる?変更できる?拡大できる?縮小できる?など10の質問からアイディアを引き出す方法
これらの手法を用いることで、従来の思考の枠を超えた創造的なアイディアが生まれやすくなります。特に初めてのワークショップでは、比較的シンプルなブレインストーミングやマインドマップから始めると良いでしょう。
1-5. メンバー間でのアイディア共有
アイディア出しが終了したら、グループを作りメンバー間でアイディア共有の時間を設けます。この時間は単なる発表の場ではなく、お互いの声に耳を傾け、対等な対話の場を共に創る重要な機会です。効果的なアイディア共有のための手法としては以下のようなものがあります:
• ストラクチャードラウンド: 順番に一人ずつアイディアを共有し、全員に均等に発言の機会を与える方法
• ギャラリーウォーク: 各自のアイディアを壁や模造紙に貼り出し、展覧会のように見て回る方法
• ワールドカフェ方式: 小グループで議論した後、メンバーを入れ替えて議論を続ける方法
• デジタルツールの活用: MiroやMuralなどのオンラインツールを使い、視覚的にアイディアを共有する方法
この時間で留意しておくべきポイントは、必ずメンバー全員が共有できるようタイムマネジメントすることおよびアイディアに対して、反対や批判をしないというルールを共有しておくことが重要です。情報の検索や探し方、共有の仕方について事前に説明しておくと、より円滑に進行できます。
1-6. アイディアのブラッシュアップ・議論
アイディア共有の時間とは区別して、アイディアのブラッシュアップのための議論の時間を設けましょう。この段階では、出されたアイディアをさらに発展させるために、参加者全員で建設的な対話を行います。以下のようなフレームワークや手法が役立ちます:
• SCAMPER法: 代替(Substitute)、結合(Combine)、適応(Adapt)、修正(Modify)、他用途(Put to other uses)、削除(Eliminate)、逆転(Reverse)の観点からアイディアを発展させる
• PMI分析: アイディアのプラス面(Plus)、マイナス面(Minus)、興味深い点(Interesting)を整理する
• Six Thinking Hats: エドワード・デボノの「6つの思考帽子」を使い、異なる視点(事実、感情、警告、利点、創造的思考、思考プロセス)からアイディアを検討する
• 5W1H分析: Who(誰が)、What(何を)、When(いつ)、Where(どこで)、Why(なぜ)、How(どのように)の観点からアイディアを具体化する
発表に向けた有意義な時間となるよう、進行役や記録係などの役割を参加者で分担し、共同作業として取り組むことをおすすめします。また、アイディアを視覚化するためのデザイン思考ツールやテンプレートを用意しておくと、議論が活性化します。
1-7. チーム内でまとめたアイディアの発表
最後にまとめたアイディアの発表の時間をとり、ワークショップの成果をアウトプットします。発表においても、全員が発表者となるようルールを共有しておくことで、参加者の主体性が高まります。
プロのようなプレゼンテーションではなく、アイディアの本質や魅力を伝えることに重点を置くよう伝えると、参加者の発表への不安が軽減されます。発表形式も口頭だけでなく、スケッチ、ロールプレイ、プロトタイプの展示など、テーマに合った多様な表現方法を認めることで、創造性を引き出せます。
1-8. 参加者に対してフィードバックや振り返りの時間を作る
発表の後には必ず、フィードバックや振り返りの時間を設けましょう。この時間はとても重要で、他のグループの参加者の意見や考え方に触れることができたり、ワークショップ全体を通じた学びを深める貴重な機会です。参加者全員で対話しながら体験を意味づける時間として、以下のような手法が効果的です:
• KPT法: Keep(続けたいこと)、Problem(問題点)、Try(次に試したいこと)を整理する
• 学びのジャーナル: 「わかったこと」「わからないこと」「もっと知りたいこと」を書き出す
• アクションプランニング: ワークショップで学んだことを日常にどう活かすかを具体的に計画する
• 感謝の輪: 参加者同士が互いの貢献に感謝を伝え合う時間を設ける
• コルトハーヘンのALACTモデル: 行動(Action)、振り返り(Looking back)、本質的な側面への気づき(Awareness of essential aspects)、代替案の創造(Creating alternative methods)、試行(Trial)の5段階で学びを深める方法
特にコルトハーヘンのALACTモデルは、体験を通じた学びを深めるのに効果的で、「何が起こったのか」「なぜそうなったのか」「どのような本質的な気づきがあったか」「次回はどうするか」というステップで振り返ることで、単なる感想や表面的な振り返りにとどまらない深い学びを参加者全員で創り出すことができます。
ここが重要!押さえておくべき事前準備のポイント
ワークショップを成功させるうえで、欠かせない事前準備にはいくつか押さえておくべきポイントがあります。限られた時間で効率よく事前準備を進めるためにも、参考にしてみてください。
2-1. 当日のテーマ・プログラムを決める
ワークショップのテーマ・プログラムを決めることは、開催側にとっても重要です。そしてワークショップの関係者全員に共有することで、ワークショップの成功への第一歩となります。
プログラム設計はワークショップのテーマから逆算して、どのセクションにウェイトをおくべきかを考慮し、参加者の学びの濃いプログラムを設計しましょう。特に講座としてのワークショップでは、参加者が予約で探しやすく、魅力的なタイトルと内容にすることが重要です。
2-2. 当日の大まかな予定表を作っておく
ワークショップの予定表は参加者および、運営するスタッフにとって必要不可欠なものです。進行が予定より進んでいるのか遅れているのかを判断できるので、スムーズなワークショップ運営ができます。
予定表作成の際には、各セクションの時間を適切なバランスで取ることで、参加者の満足度の向上が期待できます。
2-3. 適切な会場や環境を用意する
ワークショップの参加人数に沿って適切な会場の用意、受講体制を整えることも重要です。ワークショップの内容によって、1人の作業スペース、グループの作業スペースが充分に確保できる環境を用意しましょう。
また運営や講師を外部委託する場合は、委託先と十分にすり合わせを行い、トラブルが発生しないよう準備を進めましょう。会場の予約システムも確認し、参加者がスムーズに利用できるようにしておくことが大切です。
ワークショップを効率的に進めるための工夫4つ
ここまでワークショップの実施や事前準備について紹介してきましたが、より効率的かつスムーズにワークショップを進めていくtipsをご紹介しますので、参考にしてみてください
3-1. グループ内の役割を明確にする
1つ目はグループワークにおいて一人ひとりの役割を明確にしておくことがワークショップ運営の効率化につながります。グループ内で役割を分担する際のポイントとしては:
• 進行役: 対話を促進し、全員が発言できるよう配慮する役割
• タイムキーパー: 時間管理を担当し、各セクションが予定通り進むよう注意を促す役割
• 記録係: 議論やアイデアを記録し、グループの思考を可視化する役割
• 発表者: グループの成果を全体に発表する役割
• 質問係: 「この意見はどういう意味?」など、明確化を促す質問をする役割
• 盛り上げ役: 積極的に反応し、アイディアに肯定的なフィードバックを示すことで、意見を出しやすい雰囲気をつくる役割
運営側が事前に役割を指定しておく形がスムーズですが、参加者の主体性を尊重し、参加者に役割を決めてもらう形にすると、各グループに個性が生まれ、より対等で創造的な対話が生まれやすくなります。
「盛り上げ役」の追加によって、特に最初は発言をためらいがちな参加者も安心して意見を出せる環境が作りやすくなります。この役割を担う人が「それいいね!」「面白い視点だね」などと肯定的な反応をすることで、グループ全体の心理的安全性が高まり、創造的な対話がより活性化するでしょう。
3-2. 意見の出やすい雰囲気作りに徹する
心理的安全性の高い雰囲気作りも重要なtipsの一つです。参加者全員が安心して発言できる場を共に創るための工夫としては:
• 「Yes, and…」の原則: 他者のアイディアを否定せず、「いいですね、だとしたら…」と発展させる方法
• ブレインライティング: 発言ではなく、まず各自が付箋やカードにアイディアを書き出す方法
• 空間デザインの工夫: 参加者が対等に話せるよう、円形や島型の座席配置にする
またワークショップの内容によって、机や椅子の位置を変えたり、BGMを流すなどの環境面の工夫も考えられます。特にデザイン系のワークショップでは、創造性を刺激するような雰囲気づくりが重要です。
3-3. フィードバックや振り返りの時間を大切にする
ワークショップ「楽しかった」だけで終わらせてしまうのはもったいないことです。ワークショップ後の日常生活にどう活かすのかを参加者同士でシェアしながら考えを深めていくことが、行動の変化を生むきっかけとなります。効果的な振り返りの場を作るためのポイントとしては:
• 構造化された質問: 「最も印象に残ったことは?」「明日から実践できることは?」など具体的な問いかけ
• 振り返りシートの活用: 学びや気づきを整理するためのワークシートを用意
• 相互フィードバック: 参加者同士が互いの貢献や成長点についてフィードバックし合う機会
• コミットメントの宣言: 「私は〇〇します」と具体的な行動宣言を全体の前で行う
3-4. 柔軟な場づくりと即興性を大切にする
ワークショップの準備は入念に行うことが大切ですが、同時に現場での柔軟性と即興性も成功には欠かせない要素です。本当に意味のある場は、進行役が一人で作るものではなく、参加者全員で共に創り上げていくものです。効果的な場づくりのためのポイントとしては:
• 目的は固定、プロセスは柔軟に: ワークショップの目的は明確に保ちつつも、そこに至るプロセスは参加者の状態や場の流れに応じて柔軟に調整していきましょう
• 場の雰囲気やエネルギーをよく感じる: 参加者の表情やエネルギーレベル、議論の方向性に常に意識を向け、全体の流れを感じ取りながらプログラムを調整します
• 「手放す」勇気: 時には事前に準備したエクササイズを思い切って手放し、その場で自然に生まれている価値ある対話や活動を尊重しましょう
• 実験的な場としての認識: ワークショップそのものを一つの「共同実験」として捉え、完璧を目指すのではなく、共に学び合うプロセスを楽しむ姿勢を大切にしましょう
• 共創的なアプローチ: 「進行役が場をリードする」のではなく、「参加者全員で場を育てていく」という姿勢で臨み、参加者の主体性を最大限に尊重します
このように、事前の計画と現場での即興のバランスを大切にすることで、より有機的で参加者一人ひとりの存在が活きるワークショップが実現します。真に意味のある場は、完璧な計画よりも、参加者全員がその瞬間瞬間に生じるものに共に向き合い、応答していく中で自然と立ち現れてくるものなのです。
まとめ

ワークショップの成功には、さまざまな人が関わり、協業していくことが重要です。運営を検討している人はまず、自分がワークショップに参加し、体感してみることが、うまくいくワークショップ運営の近道です。
近年では、各地でオンライン開催も含めて、より実践的に学べるワークショップがたくさんあり、注目を集めています。ワークショップの参加者をはじめ、関係者全員が意義のあるワークショップを開催することが理想といえるでしょう。
また、弊社共創アカデミーでは、組織パフォーマンス向上のための実践形式の法人研修を行っております。大企業や中小企業、行政等における風土改革・組織開発の豊富な経験から、実際に現場で効果を出した取り組みを豊富にご紹介します。ぜひお気軽にお問合せください!

